

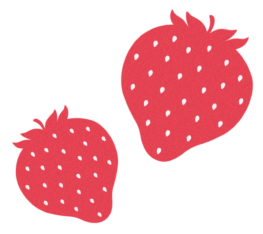

![]()
現在一般的に栽培されているイチゴの原産地は、北米東部と南米チリです。北米のバージニアイチゴと、南アメリカのチリイチゴが1700年代中期にオランダで出会い、両種の交配によって誕生。その後、ヨーロッパや北米で改良が重ねられ、世界各地に広まっていきました。
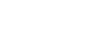
「イチゴ」という名称は、古代の大和言葉の「イチビコ」に由来すると考えられ、果実の特徴から名付けられたものと推定されています。イチビコの最古の記述は奈良時代に編纂された『日本書紀』(720年)。平安時代の『枕草子』には、イチゴ(覆盆子)の名称で2ヶ所に記述があります。

選ぶポイントは、①表面に光沢があり鮮やかで、ヘタ付近まで真っ赤なもの ②ヘタは濃い緑色で反り返っているもの ③実は、表面のつぶつぶ(痩果)を覆うように盛り上がっているもの。さらに、イチゴらしい甘い香りがするものを選ぶと、なお良いでしょう。

普段わたしたちが果実だと思って食べている部分は、じつは花托(かたく)の肥大したもの。本当の果実は、種のように表面に付いている小さな粒の部分(痩果)です。ちなみに、こうしたイチゴの花托の肥大部分と痩果は、本当の果実に対して「偽果(ぎか)」と呼ばれ区別されています。

日本には、江戸時代末期の1830年代にオランダ船によって持ちこまれたといわれ、「オランダイチゴ」と呼ばれるようになりました。しかし当時はあまり普及せず、日本で本格的に導入されたのは、明治時代に入ってから。1898年に、日本で初めて「福羽(ふくば)」という品種が育成されました。
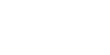
イチゴはビタミンCが豊富。ビタミンCは風邪の予防や疲労の回復、肌荒れなどに効果があります。また、アントシアニンなどのポリフェノールは活性酸素を減らし、がん予防にも効果があるといわれています。その他にも葉酸やミネラルなど、あの小さな実に、多くの栄養成分がつまっています。

2013年のFAO(国際連合食糧農業機関)のデータによると、中国が1位で、約300万トン生産しています。2位はアメリカ、3位はメキシコと続いています。日本は約16万トンで、10位にランクイン。最近では輸出も増えつつありますが、ほとんどを国内で消費しています。
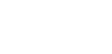
イチゴは世界各国で品種改良が行われており、多数の品種が存在します。日本で登録されているだけでも、出願登録中のものを含めると、なんと306品種(平成28年11月1日現在)もあります。今後もおいしいイチゴがたくさん誕生していくことでしょう。
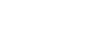
イチゴの赤い色は、アントシアニンという色素に由来しています。実が未熟なときは葉と同じ緑色をしていますが、これは葉緑素という色素によるもの。実が熟するにつれて、葉緑素が分解され色が抜けて白くなり、その後、太陽が当たったところからアントシアニンが合成され赤くなっていきます。
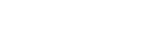
日本の自然環境の中では、主に4月上旬頃に花が咲くのですが、それは小さくて白い、とてもかわいらしい花です。鑑賞用のイチゴには、赤やピンク、桜色の花を咲かせるものもあります。実際に見てみたいという方は、自分で育ててみるのもいいかもしれませんね。
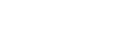
近年では、イチゴが店頭を飾るのは12月後半から5月位にかけてですが、本来の育て方である露地栽培では、春先から梅雨前までの時期に旬を迎えます。ちなみに、俳句ではイチゴは夏の季語になります。
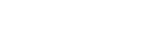
もちろん家庭菜園も可能です。ただし、現在日本で栽培されているほとんどのイチゴが、ハウスなどで加温して栽培するのに適した品種。これらの品種を家庭の露地やプランターで育てた場合、ハウスで栽培するよりも果実ができにくいこともあります。
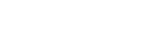
加工に適したイチゴは、スーパーに並ぶ生食用のイチゴに比べて香りが強く、色も果実の中まで真っ赤で、加熱加工しても豊かな香りと鮮やかな色が残るのが特徴です。アヲハタでは、これらのイチゴを最適なバランスで配合したり、新しい品種の研究・開発も行っています。
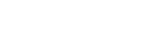
イチゴの実といえば、真っ赤なイメージがありますが、完熟しても赤くならない“白いイチゴ” が存在します。たとえば、「初恋の香り」や「雪うさぎ」、「淡雪」などの品種があり、徐々に増えてきています。
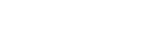
夏目漱石の『吾輩は猫である』に登場する、苦沙弥先生が「俺はジャムは毎日舐めるが…」と言っているシーンがありますが、漱石自身もイチゴジャムが大好物だったと知られています。イギリスに留学経験のある漱石は、そこでおいしいジャムに出会ったのかもしれませんね。
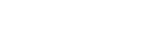
イチゴが多くのツルに囲まれている事からイメージされたといわれる「幸福な家庭」をはじめ、「尊重と愛情」、「先見の明」といった言葉があてられています。誕生日ケーキに花言葉を添えてみる、など、贈りものの参考にしてみてはいかがでしょうか。
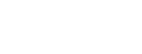
2015年に福岡県の中尾浩二さんが栽培したイチゴが、最も重いイチゴとして、32年ぶりにギネス世界記録を更新しました。重さはなんと250g!長さ12cm、幅8cm、外周は25~30cmほどです。中尾さんは突然変異の現象を知ったうえで、意図的に巨大なイチゴの栽培に挑戦していたようです。
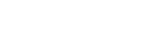
イチゴの生食での消費量は、日本が世界一ともいわれています。16歳以上の国民3,600人を対象にしたNHK放送文化研究所の調査(2007年)によると、日本人が最も好きな果物はイチゴで、約75%もの人が好きという結果が出るほど、イチゴは日本人にとって魅力的なものなのです。
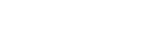
ズバリ、イチゴは先端にいけばいくほど、甘いです。糖度を比べると、先端はヘタの部分よりも1%ほど糖度が高いというデータがあります。その理由は、イチゴが育つときに、果実の部分が先端から成熟していくためです。
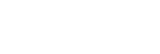
1898年、新宿御苑の農学博士であった福羽逸人(ふくばはやと)は、国産イチゴ第一号となる「福羽苺」を育成しました。当初は門外不出(皇室用のみ)とされ御苑イチゴ、御料イチゴなどと呼ばれ、およそ庶民には手の届かない存在だったそう。いまや、すっかり国民の人気者になりました。